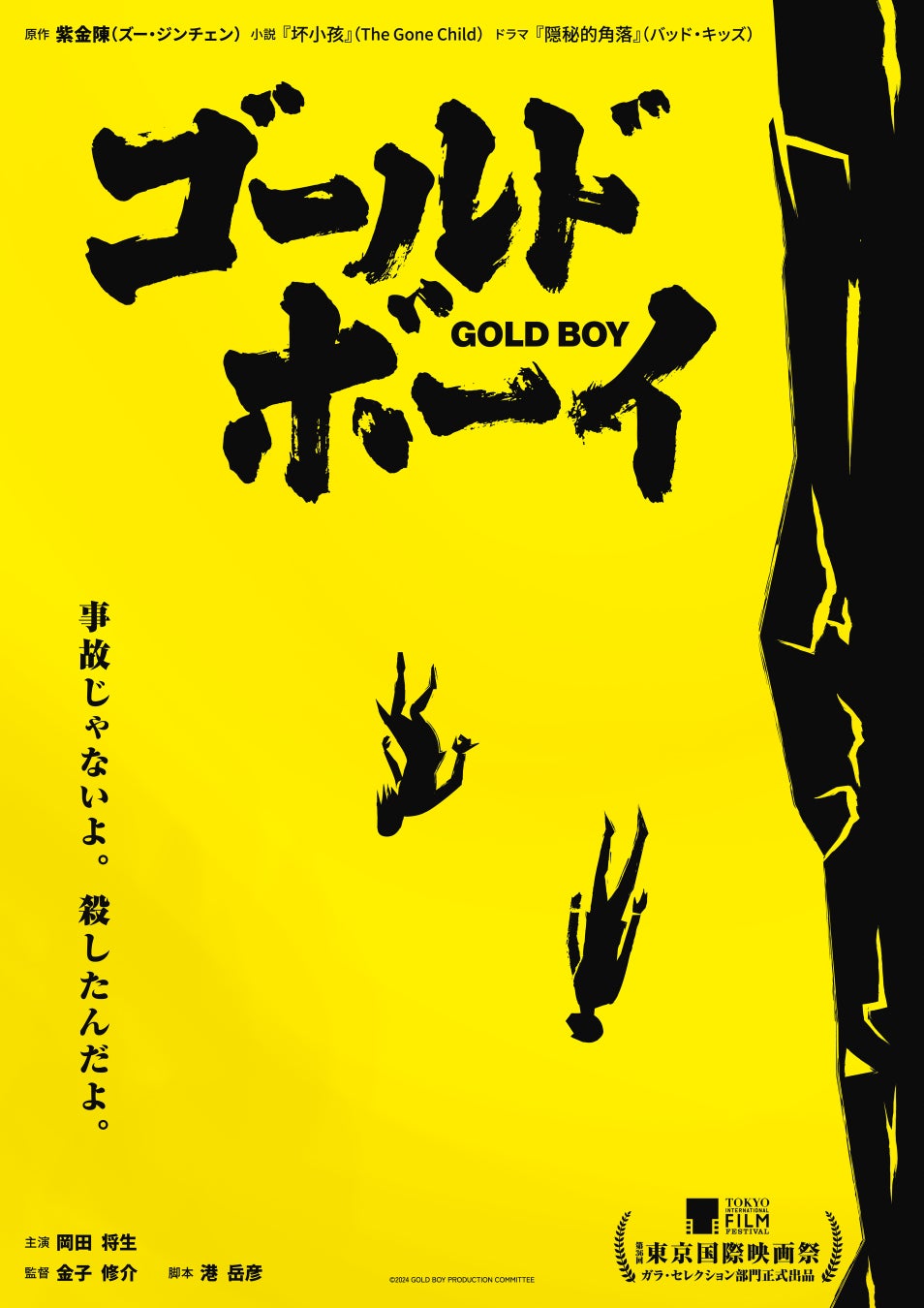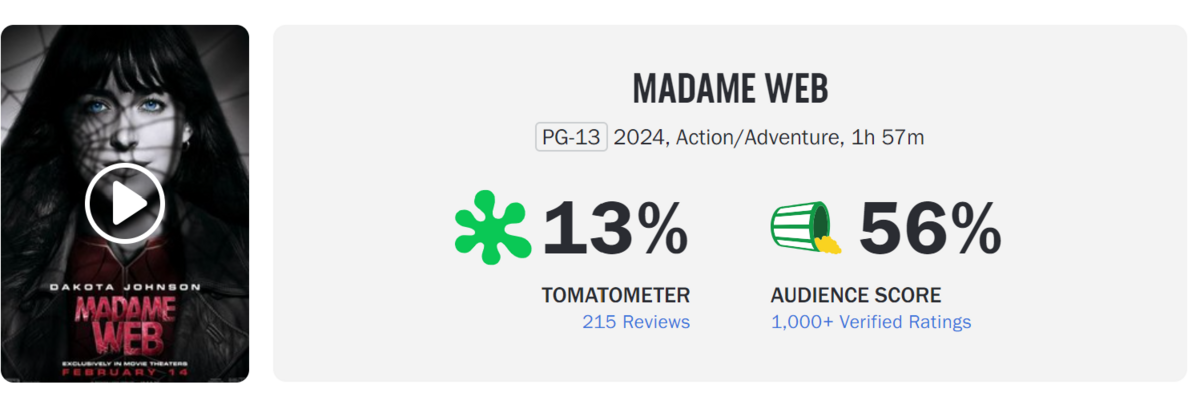『変な家』っていう本が書店に並んでいるのは認識をしていたが、実際に殺人事件があった家とか法律とか増改築の制約によって魔改造された間取りになった家とか実際に存在する・した家を紹介する『怖い絵』の続編だとずっと思っていてスルーしていた。なぜなら『変な家』の作者のもう1作の『変な絵』も一緒に並んでいたからだ! これは同じようなシリーズ作品と誤解するのも無理もない。
そんな私の『変な家』との出会いは、昨年の初秋くらいの時期である。『コワすぎ!』を劇場で観たあとに『近畿地方のある場所について』を読破した時期である私はホラーモキュメンタリーに飢えており、もろもろ書店を彷徨ったところこの作品がそのジャンルに位置付けられるものであると知った。買って読んでみたら面白かったので、『変な家2』と『変な絵』も買って読みました。
小説といえど、ごりごりの文学作品というわけでもなく、しばらく活字から離れていたアラサーにとっては本の面白さを改めて知らしめてくれるよい機会となった。このインターネットが跋扈し人の集中力が5分も続かずイントロはどんどん消滅していくこの時代に、読みやすい筆致体で書かれつつも、人間の恐ろしさが感じられるジメジメした日本のサスペンス・ホラーという作品で、かなり楽しむことができた。
『変な本』は、オカルト雑誌のライターがおかしな間取りに隠された事実を解き明かしていくという作品である。そのため、小説というよりはオカルト雑誌の記事あるいは手記のような、モキュメンタリー形式の作品である。まさにオカルト雑誌の記者という設定は、書籍という媒体にピッタリなもので、ところどころ思い出すように差し込まれる間取り図も親切でわかりやすい。かつ、終盤には人間の業のようなものも感じられて、ゾッとするオチも用意されている名作である。
さて、そんな『変な家』が映画化するというので、今度は映画という媒体を活かしたガチモンのホラーモキュメンタリー映画が爆誕するぞ!と思っていたところ、(まあ予告編とかキャストの段階でわかっていたことなんだけれども)そんなことはなく、10代前半向けのホラーチック娯楽映画と成り果てていた。さらに終盤の展開はかなり魔改造されており、さながらバイオハザード4の低予算実写版のようであった。終盤の因習村シーンの美術や衣装はとてもそれっぽくサイコーなのだが(『女神の継承』とか『呪詛』を思い出した)、それがゆえに子ども向けに振り切ってしまったのが残念だと感じた。そのせいで本家が変な間取りであるという設定が全く活かされていない。村人が総出で客人を殺しにくるならそもそも変な間取りを作ってこっそり人を殺す必要もないだろ!と突っ込みたくなる。さらに終盤の怒涛の展開はたしかに妥当なのだが、チェンソーを持ったババアが現れたと思ったら石にチェンソーがハマって動けなくなったり、大怪我をした本家の人間がなぜか復活していたり(早すぎて俺じゃなきゃ見逃しちゃうねレベルで動いていることになる)、レンタカーを因習村に放置していたりなど、なかなかツッコミどころが満載である。近くの席の小学生ですらツッコんでいた始末である。
とはいえ、小学生の集団がジャンプスケアや肉体欠損描写にビビっていたり、終劇後に「楽しかった〜」と話しているキッズをみたり「これでもうホラーは大丈夫だ!」みたいなことを話している小学生をみていたら、これはこれでいいんじゃないかという気がしてくる。次世代にホラーやモキュメンタリーの面白さを伝える役目を少なからず果たしており、このジャンルの新しい才能を発掘しファンダムを拡大する意義があると思う。それこそが、もともとの原作が子どもが好きなメディアのYouTubeという媒体である意味であるのではないだろうか。まあ、劇中の会話も気にならないくらいの感じで映画を見てたということでもあるのだけど。
先に述べたとおり、YouTuberを主人公としてその動画や取材用素材を組み合わせた骨太のガチモンのモキュメンタリー作品としてまとめたらかなり面白くなったような気がする。俳優の演技や美術、衣装などのディテールは優れていただけに、残念な作品ではあるが、子ども向け作品としては花マルだろう。